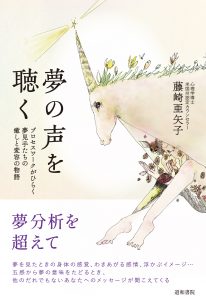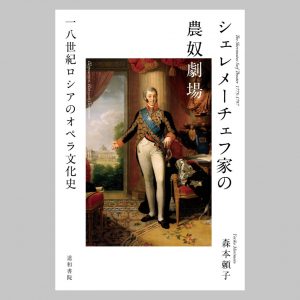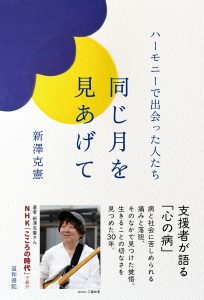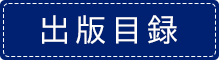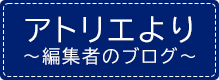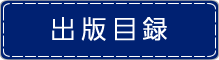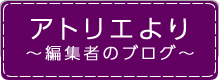お知らせ一覧
編集者のブログを更新しました久しぶりの更新です。 「全訳と解説」の最新刊 |
『夢の声を聴く』刊行記念
|
関連の催し
|
『夢の声を聴く』
|
冬季休業のお知らせ12月27日(土)~2025年1月4日(日)まで、冬季の休暇を頂きます。 休業期間中にご注文頂いた書籍は、1月5日(月)より、順次、発送させて頂きます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
|
書評掲載
|
テレビで紹介
|
書評掲載
|
書評掲載
|
夏季休業のお知らせ8月13日(水)~8月17日(日)まで、夏季の休暇を頂きます。 休業期間中に fax 等で頂いたご注文は、8月20日(水)の取次搬入となります。 また小社オンラインショップで8月12日(火)午後3時以降に頂いたご注文につきましては、18日(月)より順次、発送をさせて頂きます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 |
全229件中 1~10件目を表示