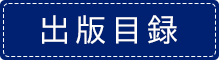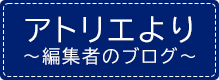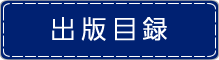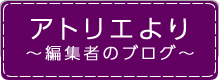部決と繰り延べ
毎年この時期は、新年度の採用教科書(業界用語では採用品)の出荷で、いそがしい。
いえ正確にいえば、忙しいのは、在庫の管理と出荷の業務を委託している倉庫。
こちらが採用品で忙しいのは、例年、11月から2月ごろまでです。
お正月休みが間にあるので、「まるっきり新刊」の教科書をつくるときは(たいていは原稿が遅れるので)けっこう悲惨な年末年始になります。
採用品で悩ましいのは、
・どのくらい重版するか、「部決」問題。
・取次から支払われるはずの売上金、これが「繰り延べ」になる問題。
部決(ぶけつ)とは重版する部数(冊数)を決定すること。
納品のデッドラインがあるのに、重版部数をぎりぎりまで決めない出版社もあるそうで、印刷所の担当者さんはこの時期は心身とも大変そうです。
部決に慎重になるのには理由があって、
・大学生協などからの注文は履修定員どおりに、来る。が、「ふたを開けてみたら」履修生が少ない
・教科書を買わずに済ませる学生さんも多い
というのがよくある。ありすぎる話。
で、返品が多くなり、重版した分が、余ってしまう。
余りをできるだけ避けるために、慎重に注文数・出荷数の見極めをする。
一方で、教科書は改訂していくものなので、来年度も販売できると考えていると、「改訂」であえなく断裁(だんさい。廃棄処分)ということも起こります。
もう一方で、
とくにコロナ禍以降、採用数が年によって変動していて(大きくは減少傾向ですが)、冊数の見通しが立てにくい。
いろいろあるので、うちでも採用品の重版の部決は、ひとしきり考えます。
考えますが、他社さんに比べると「ゆるい」かもしれません。
間に合うかどうか、ハラハラするような仕事はお互いやめましょう。
という気持ちもあるし、
もしも「ちょっとだけ足りない」という事態になったら、緊急で重版することになる。
その手間と費用を省きたい。
なにしろこちらは少人数ですから…
どこに「ムダ」を許すか。
そういう発想のちがいだと思っています。
もう一つの、売上金「繰り延べ」問題。
これについては、いろいろ差し障りがあるので、小さな声ですこしだけ語ります。
大手取次から、毎年、電話で、3月末締の採用品の売上について、支払の一部を繰り延べたい、と依頼があります(以前は「保留」と言っていた)。精算は9月末。
要するに、半年間、出版社には、売上金が入ってこない。
一部とはいえ、決して少なくない金額です。
なぜこういうことが起こるのか。上記の「返品」問題がからんでいます。
履修の定員どおりの数を出荷する、しかし必然的に返品も多い。
そこで、後期が始まる9月まで待って、返品が落ち着いてきた頃に、支払いますよ。
という、合理的なやりかたではあるのですが…
問題は、その金額が、ずーっと、変わらないということです。
少子化等で、採用品の売上そのものが、出版界全体で、減っている。
出版社としては、書店から来る注文数を前年の数字から予想して重版し、注文通りに出荷する。
返品が多いとしても、出版社の責任ではありません。
一方、重版にかかった費用は、3月末・4月末に、印刷所に支払わねばならない。
紙や印刷など制作費の高騰は続いている。
もう一方で、書店も経営が苦しいため、返品が早くなっていて、5月末からサミダレ式にくる。
取次からの月々の支払は、「納品-返品」の金額なので、採用品の返品によって、春から夏にかけての売上が、けっこう大きく、食われてしまう。
それで、何年か前から、
・繰り延べの金額を、状況を鑑みて減額してほしい
・期間を短縮してほしい
と要請しています。
窓口の担当者さんの様子では、多数の出版社からそういう要請を受けていることが察せられます。
が、改善の動きは鈍いです。
来年は、どうなっているでしょうか。
(ふ)
-300x218.jpg)